木星
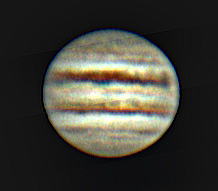
土星
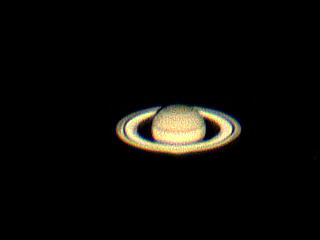
2020年8月5日
撮影機材
VC200L
ZWO
ASI 290MC
color : RGB24
6,117Fr(木星)
5,431Fr(土星)
RegiStax6,、ステライメージ7
場所 : 自宅
惑星の観測結果です
(写真はクリックで拡大)
木星 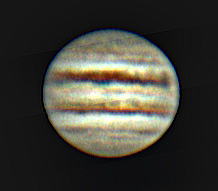 土星 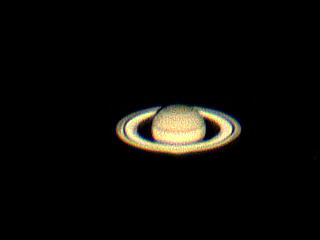 |
撮影日 2020年8月5日 撮影機材 VC200L ZWO ASI 290MC |
SharpCapture color : RGB24 6,117Fr(木星) 5,431Fr(土星) RegiStax6,、ステライメージ7 場所 : 自宅 |
木星 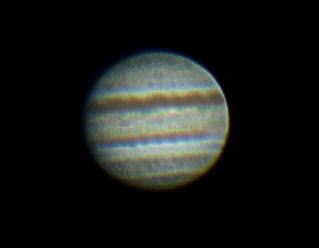 土星  |
撮影日 2019年9月16日 撮影機材 VC200L ZWO ASI 290MC |
SharpCapture color : RGB24 5628Fr(木星) 4825Fr(土星) RegiStax6,、ステライメージ7 場所 : 自宅 |
| 火星 距離 : 5,759万km 視直径 : 24” 光度 : -2.8等 |
撮影機材 VC200L Photon 3倍バーロー ADC+ IR/UVカットFilter(ZWO) ASI290MCカメラ(ZWO) |
撮影日 2018年7月29日 |
撮影日 2018年8月4日 |
撮影日 2018年8月10日 |
|
| SharpCapture color : RGB24 1,586Fr RegiStax6,NeatImage |
FireCapture color :offで撮影後 DebayerでColor化 5,747Fr RegiStax6,NeatImage |
FireCapture color :offで撮影後 DebayerでColor化 NeatImage |
|||
 |
 |
6,996Fr |  AutoStakkert3.0でスタック、RegiStax6でWavelet処理 AutoStakkert3.0でスタック、RegiStax6でWavelet処理 StellaImage8でスタック、画像処理 |
||
| 7,996Fr |  StellaImage8でスタック、画像処理 |
||||
5月31日 6時34分に火星が衝。今回は10年半ぶりの最接近(スーパーマーズ)です。その3日後に撮影しました。
同日に土星も撮影しましたが、この距離では両方とも視直径は殆ど変らず、火星の光度は土星よりはるかに明るく
木星(-2.0等)とほぼ同じでした。この日22時頃には火星と土星はさそり座近く、木星は西方のしし座に有り
スピカ、アンタレスなど含め賑やかな眺めでした。高度は残念ながらいずれも30°程度と低く高倍率観測には
不向きでしたが……。
空気が澄んで透明度は良かったが、風が強くシンチレーション大でした。気流が良ければもう少し解像度が
良くなると思われます。
①~③の写真で火星の自転(14.63°/1時間)の様子が判ります。
(2016年6月4日記)、(6月5日追記)(6月6日火星、土星位置の誤記修正)